最近は、ほんとに雨が多くなりました。
しかも、ゲリラ豪雨です。だからというわけではないのですが、外回りにおいて、一番、傷むのは、やっぱり雨樋です。
もちろん、雨樋が一軒まるごとごっそりダメになる・・・ことは少ないですが、土砂降りになると、一部の雨樋がダダ漏れ状態になったりするので、雨の日は雨樋チェックにもってこいです。
雨樋はメンテナンスありきで考えましょう
そういった経験から、やはり、雨樋を選ぶ時には、メンテナンスありきで考えておいた方が良いと思います。
まずは雨樋の種類についてです。
雨樋の種類は?
雨樋の専門家になるわけではないので、余分な情報はカットしますが、一般的な住宅において(雪の多い地域は別です)雨樋は、大きく分けて、
- 形状・材質ともに2種類ずつ
で考えておきましょう。
雨樋の形状について
雨樋の形状は、大きく分けて
- 半円型
- 角型
の二つに分かれます。
半円型よりも、角型の方が、雨水を流す量が多くなります。
ただ、半円型の方が、角型よりもお値段はお安いです。
雨樋の材質について
通常、私たちが住宅に使う雨樋の材質は、プラスチックか塩ビです。
ただし、雨樋は過酷な環境にさらされるため、
- プラスチックの場合は、補強のために形状に工夫がしてあり、
- 塩ビの場合は、補強のために芯に金属を使ってあります。
このあたりは、雨樋を選ぶ際に、一応は、知っておいた方が良いと思います。
どう?修理するか?を知っておきましょう
雨樋の形状と材質が把握できたら、次は、万が一、雨樋の一部がダダ漏れになったら?という状況を想像してみましょう。
下の写真をご覧ください。

写真ではわかりにくいですが、土砂降りの日は、ここが海のようになります。
できれば、「全部、直すんじゃなくて、悪いところだけ、直せた方が良い」ですね?
つまり、それが答えです。
悪いところだけ、直しやすい雨樋はどれでしょうか?
おすすめの雨樋は?
ここからは、V-大工の独断になります。
今まで、何度も雨樋を部分的に修理した経験がありますが、やはり直しやすいのは、芯に金属が入っている半円型の塩ビの雨樋です。
その理由は、形状が角型よりも、圧倒的にシンプル!で普遍的だからです。
そのため、製品の入手も簡単で安価です。
一方、角型は形状がとても複雑ですから、いざ!修理しよう!と思った時には、すでに廃番になっている場合もありますので、注意しましょう。
雨樋のちょっとした修理のまとめ
雨樋のコスパを新築の時に考える方は、少ないかもしれません。
ですが、それから10年、20年経った時、雨樋の修理費用に、頭を悩ますこともあります。
特に、屋根が寄棟の場合は、雨樋の距離が長く、雨樋交換の費用もバカになりませんので、ぜひ、メンテナンスのことも考えておきましょう。
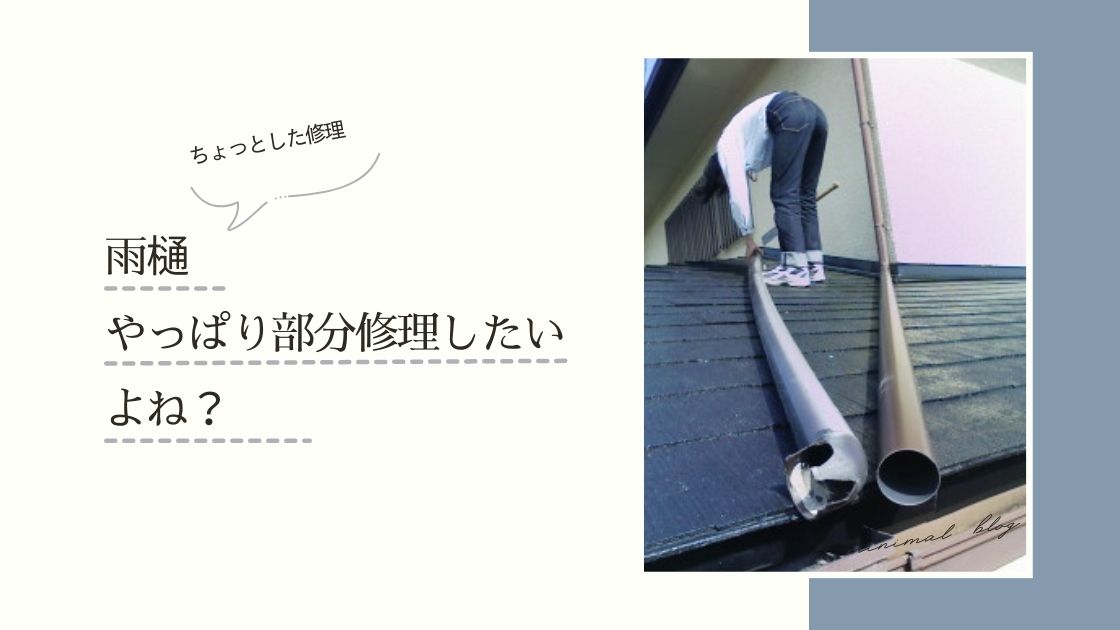


コメント