ユネスコが、伝統建築工匠の技(木造建築物を受け継ぐための伝統技術)を無形文化遺産に登録しました。
これ自体は、とても嬉しいことですが、
建築のど真ん中にいると、よくわかります。
日本の木造建築技術は、果たして残せるのだろうか?と。
目次
無形文化遺産に登録された技とは?
今回、ユネスコに登録されたのは17個の技術なのですが、
多くは、神社仏閣や白川郷の茅葺など、特別な建築技術です。
ただ、その中には、
- 左官(日本壁)
- 建具製作
- 畳製作
といった、私たちの家にも使われてきた技術が入っており、
この3つを見る限り、
日本の木造建築技術を残すのは、ほぼ絶望・・・と言っても過言ではありません。
和室が消えれば、皆、消える
上記の3つの仕事に共通しているもの。
それは、言うまでもありません。
和室です。
和室には、塗り壁があり、畳が敷いてあり、障子や襖などの建具があります。
だから、和室が消えていけば、自然と、この3職種も消えていく運命にあります。
実際、家を建てている工務店自体、
- 左官職人
- 建具職人
- 畳職人
を確保しておくのに、とても苦労しているのです。
問題は3職種だけじゃない
しかも、問題なのは、この3職種だけじゃありません。
なぜなら、
- 塗り壁
- 畳
- 建具
この3つは、家においては、仕上げなのですから。
つまり。
仕上げの仕事をする職人が減っている・・・
ということは、
仕上げ前の段階を行う職人=大工職人も減っている・・・ということに他なりません。

使えるものは使うのが移築
新築至上主義が職人をダメにした?
この点について、私は、
新築至上主義が職人をダメにした・・・
という持論を展開しています。
なぜなら、家を建てることはお金儲けであり、スピードが命になります。
だからこそ家は、現場で作るというよりも、
プレカットなど工場生産のものを使うという方向に変わってきました。
が、皮肉にも、それが、
職人を単なる家づくりロボットに変えてしまいました。
職人は、来る日も来る日も、似たような仕事をするだけで日が暮れていきます。
そうして、いつのまにか、彼らに敬意を払う人も少なくなっていったのです。
しかも、建築業界はピンハネが横行している業界です。
- 尊敬もされない。
- もらえるお金も少ない。
となれば、
当然、誰も、跡を継ぎたがりませんし、職人自身もこの仕事を子供には継がせたくないと思っています。
家は直さなければならないもの
勘違いをしないでほしいのは、
どんなに素晴らしい、メンテナンスフリーと言われる新築を建てようとも、
家は、直さなければならないものだということです。
なぜなら、
世の中に、
- 使っても劣化していかない
- 年数が経っても劣化していかない
そんなものは、存在しないからです。
職人が消えていくと、どうなる?
にもかかわらず、
職人が消えつつある今の現状には、まったく歯止めがかかりません。
おそらく、今後、家は直せなくなっていくと思います。
もちろん、リフォーム業者を名乗る輩は存在するでしょう。
しかし、
職人のレベルが低くなれば、
古い部分を残しつつ、必要な部分だけの改修で済ませる。
なんてことはできなくなるのです。
結果、
リフォームと言えども、できるだけ新築に近づけさせるやり方が横行します。
つまり、壊せるだけ壊し、全部一から作り直す・・・というやり方です。
まとめ
残念ながら、上記のことは、未来の話ではなく、ほぼほぼ現実です。
1年や2年で本物の職人にはなれないのですから、当然の結果でしょう。
だからこそ、
今、工務店側は、職人がいらない工法や、職人がいらないやり方を模索しています。
が、それは、単なる一時しのぎであって、大局的には、正しい選択だとは思えません。
私自身、今まで、工務店側には、微力ながらもいろいろな働きかけをしてきました。
でも、最近、気づいたんです。
率先して古い家を壊しているのは、工務店自身なのだ・・・と。
多分。
今、この由々しき事態を止める方法はたった一つしかありません。
「古い家を直して住みたい!使えるものは使いたい!」
本気でそう思う人が増えてくれること。
そう声を上げてくれる人が増えること。
それを願って、ブログを書いています。

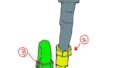

コメント